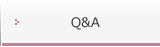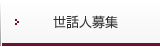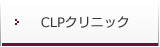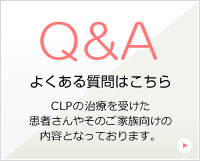以下のQ&Aは、主に、既に治療をお受けになっている患者さんとご家族を対象としています。 詳細につきましては、主治医にご確認下さい。
育成医療について
公的援助について教えてください。
医療費援助の公的制度(例:福岡県)には下記の制度がございます。
1. 乳幼児医療支給制度
小学校に就学する前までの乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、子育て家庭への支援の充実を図ることを目的とした制度です。
2. 育成医療制度(自立支援医療)
身体に障害のある児童または現状を放置すれば将来障害を残すと認められる18歳未満の児童(先天性および後天性の心臓障害、腎臓障害ならびに先天性内臓障害を含む)で、生活能力を得るため、短期間で治癒または軽快の見込みのある人に対し、指定医療機関で治療を受ける費用を公費で負担する制度です。
3. 更生医療制度(自立支援医療)
身体障害者手帳をお持ちの人で、障害の部分を手術したり、治療したりすることによって、障害の程度が軽くなり、職業上、日常生活上の能力が高まることが期待される場合には、厚生労働大臣または知事が指定した医療機関で医療を受けることができます。
4. 医療費控除
医療費控除は、みなさんやご家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
哺乳床(ホッツ床、NAM:ナム)について
ホッツ床を装着してから、病院に来る頻度はどのくらいですか。
初めての来院からホッツ床(またはナム)ができるまでは数日以内、その後は調整のために1~2週間に1回の来院になります。唇裂、顎裂を閉じる手術が終わった後は、虫歯や歯並びのチェックや予防で1~数カ月に1回の来院になります。
ナムの固定用のテープで顔の肌がかぶれてしまいます。
テープの種類がいくつかありますので、低刺激のものを試してみて、お子様に合うものを探してみてください。また、貼りかえるときはテープが毎回同じ位置にならないように、できる範囲で工夫してみてください。お風呂に入る時間などを利用して、1日1回はテープをとって皮膚を休ませるのも良いでしょう。九大病院の売店でベージュ色のテープを販売しています。
その他
哺乳びんの乳首の選び方は?
吸う力が少なくても飲めるように工夫された口蓋裂用のものや、月齢に応じて、段階的に吸う力が必要になるものがあります。選ぶ目安のひとつは、20~30分で必要量を飲めるのに適しているということです。哺乳によって筋肉の発達を促せるよう、当院では来院時に飲む量や哺乳にかかる時間を確認しながら、赤ちゃんの状態に合った乳首を選んでお勧めしています。
歯みがきはいつから始めますか?
歯ブラシを使い始める時期は、上下の前歯が生えそろう1歳くらいが目安です。また、歯が生え始めて間もなくから、夜の就寝前はお白湯を飲んで口の中を洗い流したり、ガーゼで口の中を拭き取ることなど、お口の中を清潔に保つ習慣づけも大切です。
スピーチエイドを外したとき鼻声が再開したり、思春期になるとどのようになるのか気になります。
思春期に鼻声が出てきたとき、アデノイドが消失したとき、精神的な問題(鼻声が増してきたときの心の傷)が生じてきたときに、スピーチエイドを使用すると状況が改善することがあります。
現在5歳。瘻孔(口蓋の穴)がありプレートを付けましたが、矯正治療のため装置を外しました。生活に支障はないですが、瘻孔をふさぐべきでしょうか。
1. この時期の矯正治療は長くはないので、生活に支障がなければプレートを一時的に外します。鼻漏れなどの問題があるときは、遠慮なく主治医に相談して下さい。
2. 9-10歳頃に骨移植をする際に、同時に瘻孔をふさぐことが多く、その方が経過も良いようです。
1歳5カ月の双生児。姉の方が話が上手です。?今後どのような言語指導になるのか教えてください。
口唇口蓋裂の子供さんには、言葉の発達が遅い人が多いようです。他の全般的な発達が遅いとか、聞こえに問題があれば当てはまりませんが、一般的には言葉の発達は追いついてくることが多いと考えられます。
1. 口蓋形成手術後、発達の検査などを行い、ブローイング(吹く)などの練習を行います。
2. 1歳半から4歳の間は、言語訓練の準備を月1回くらいの割合で進めます。
3. 4歳頃から鼻咽腔閉鎖機能や構音の検査などを行い、半数は積極的な治療をします。